
まき網漁具の概要

まき網漁具は漁獲対象とする魚や網を搭載する船のトン数によって、漁具サイズ、目合などが変わってくる。下記に一例を示す。
| 漁法 | 魚種 | 大きさ |
| 海外まき網 | カツオマグロ類 | 長さ1500K(2250m)×深さ230K(350m) |
| 大型まき網 | マグロ類 | 1000K(1500m)×深さ280K(420m) |
| 中小型まき網 | アジサバ類 | 長さ750K(1125m)×深さ240K(360m) |
あくまで参考程度だが上記の通りとなる。

浮子は強力な油圧機器の力に耐えられるEVA素材が主流で沈子は、鉛入ロープ、カバー沈子が主流となりつつある。

まき網漁具の名称は地区によって様々な呼び方があるが、一般的な名称を下記の通り示す。
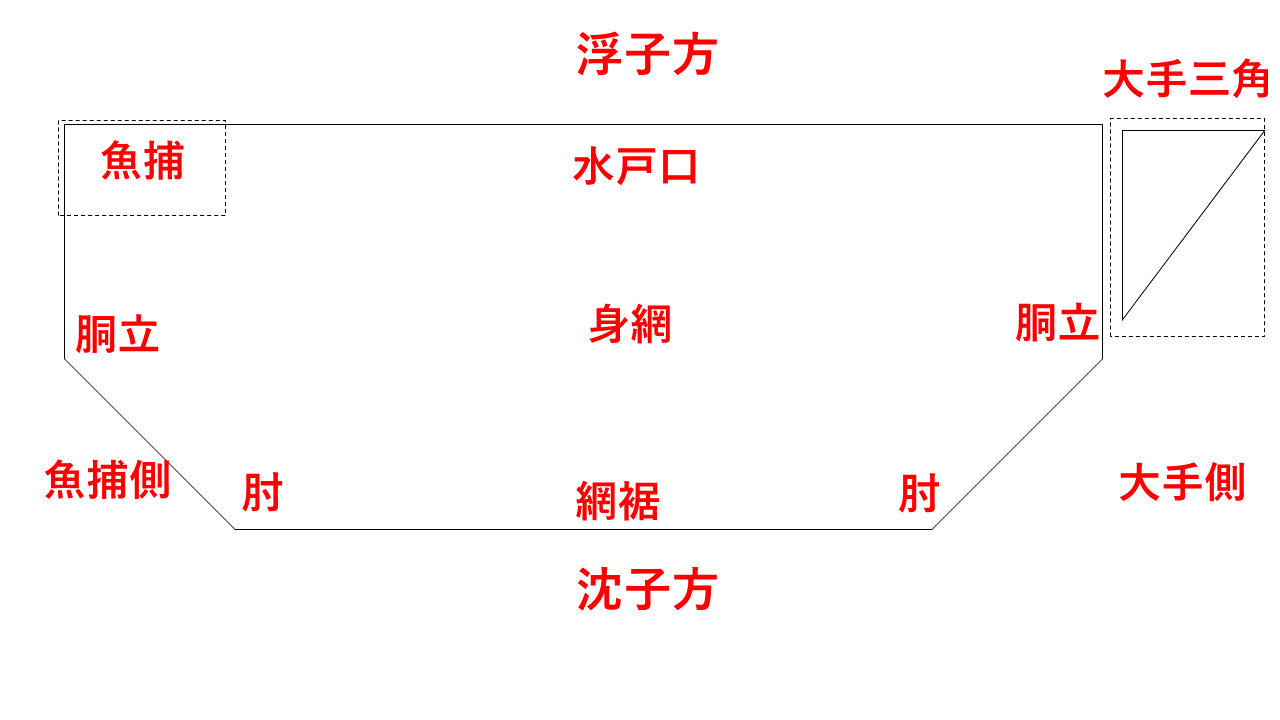
19tまき網の浮子、沈子について

浮子について
19tまき網で一般的に用いられているEVA浮子は2~3kgだが、網漁具中央部の沈み込みを軽減するため中央部に4kg浮子を配置する場合もある。
網部分の1胴(1町)が10Kの場合は浮子方の長さは1胴(町)7K、沈子方の長さは1胴(町)8Kとなる。

岩について
まき網漁具は網の部分ごとに重量配置が変わってくる。
小型のサバ、イワシ類を漁獲する漁具の重量配置は細かい範囲で強弱を付ける必要は無く、下記の図のように大まかな設計で良いといわれている。
一方、投網時に深く潜っていくといわれる大型のアジなどを狙う場合は重量配置を細かく変えていく必要があるといわれる。
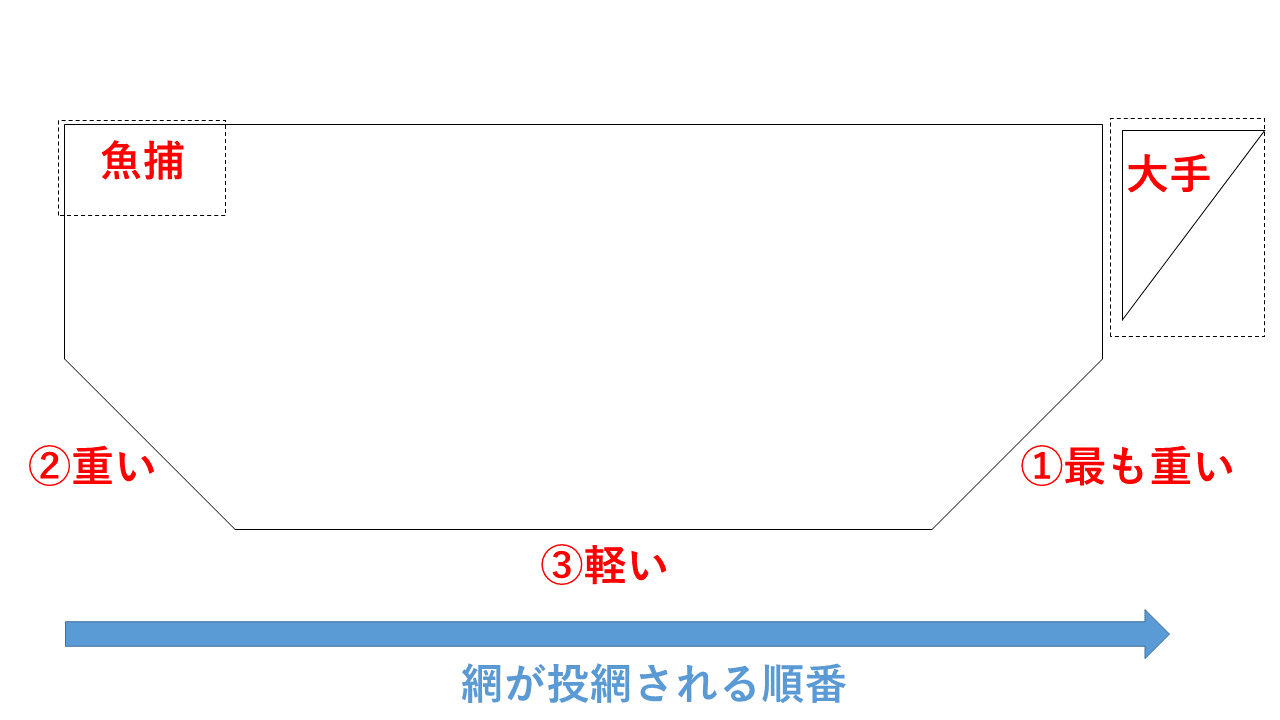
魚捕は最初に海中に入る網であり素早い沈降、網の展開が求められるため漁具全体で2番目に重たい沈子重量となっている。魚捕は魚が最後に溜まる部分でもある為、太い網地が用いられている。太い網は潮流抵抗を受けやすいため、重たい沈子をつけて素早く沈めなければならない。

魚捕から大手に至る網地の中央部は深さが一定に設計されており、魚捕と比較して目合が荒い網地となっている。身網は魚捕よりも潮流の影響を受けにくい為、最も軽い沈子重量となってる。
大手部は最後に投網される部分であり魚捕、身網の沈降に追いつくようにするため、最も重い沈子重量となっている。

このように沈子重量を部分ごとに変える事で網漁具が海中でスムーズに沈み、展開されるようになっている。

実際の漁業現場ではこのような設計条件に加え、波浪の状況、上層、中層、下層で向きや速さが異なる潮流、網船本船の漁労機器の能力等を加味し操業が行われている。
まさに神業を駆使し、漁師さんは魚を獲っている。
身網から魚捕に至るまでの網地規格について
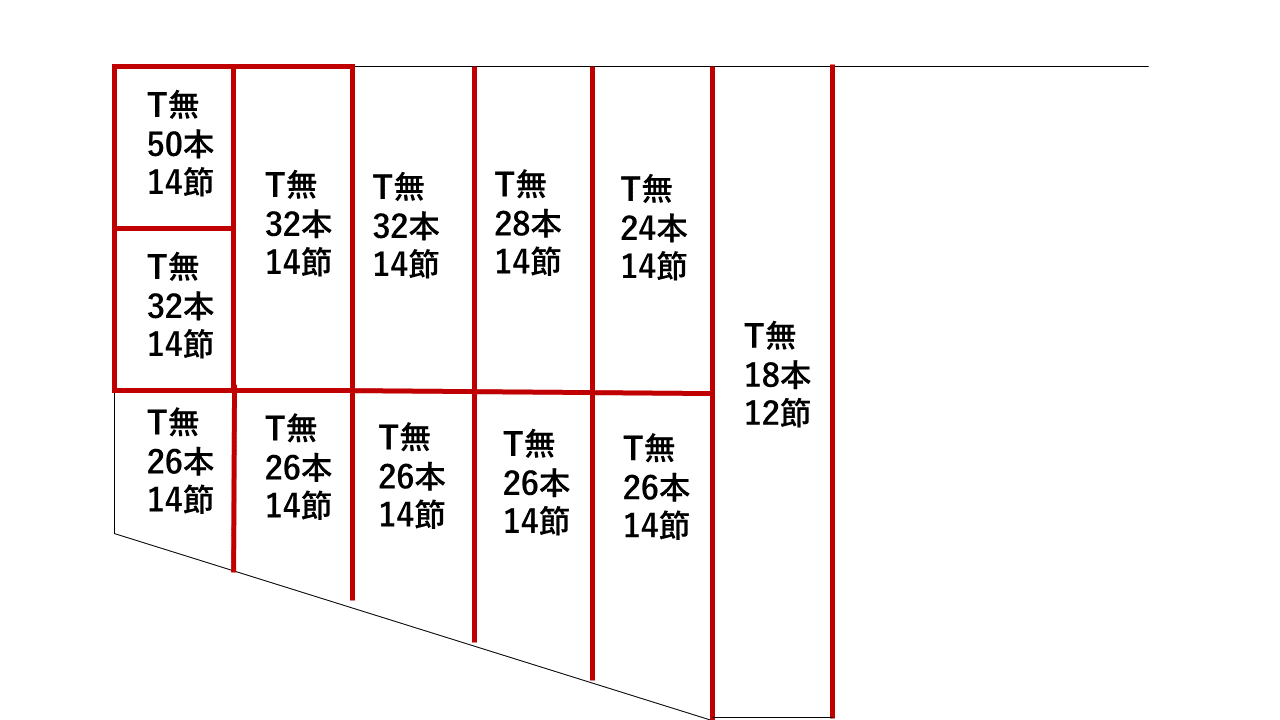
魚捕部の網の入れ方の一例は上の簡易図面のようになる。
一般的に50本の網と18本の網を縫い合わせるようなことはせず、18本⇒24本⇒28本⇒32本⇒50本といったように太さを段階的に太くしていきながら仕立を行う。
太さに差がある網を仕立て合わせると互いの網の強度が一定で無いため、破網のリスクが高まってしまう。

大目(荒目)の導入
従来のまき網漁具は身網のほとんどを小さな目合で構成することが多かった。その方が魚を効率的に包囲し、たくさん漁獲できると考えられていた。
しかし、近年は悪潮流へ対応及び漁具の包囲容積を確保する為に90~150㎜の大目網を部分的に用いる事例が多い。
下記に漁具の事例を示す。

このような事例の通り、浮子方、沈子方に大目を1~2枚入れる事例が増えている。浮子方の大目は悪潮流化で浮子なりが崩れることを防ぎ、沈子方の大目は潮流の抵抗を受けづらく、網漁具の沈降を促進する。
 小型の魚が抜けていってしまうという懸念もあるが、このような漁具設計は全国各地で受け入れられている。この点を鑑みると抜けている魚はごく一部であり、漁業現場において大きなデメリットとは考えられていない。
小型の魚が抜けていってしまうという懸念もあるが、このような漁具設計は全国各地で受け入れられている。この点を鑑みると抜けている魚はごく一部であり、漁業現場において大きなデメリットとは考えられていない。
大目導入により漁具性能が向上するメリットの方が大きいと考えられる。

今回紹介した内容は漁具設計における考え方のごく一部ですが、まき網漁業者様のお役に立てると幸いです。





